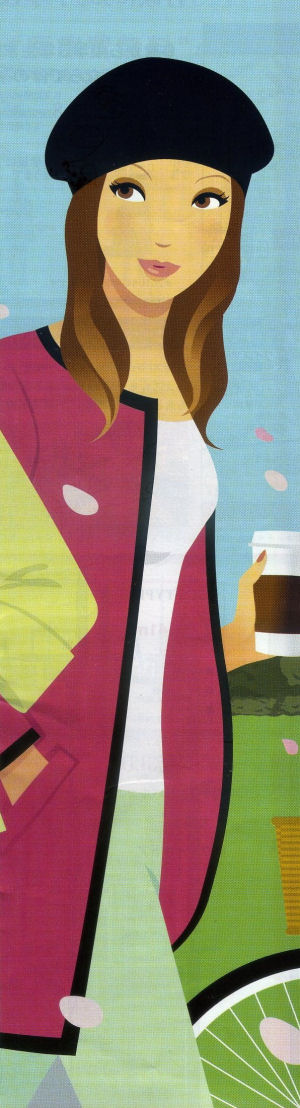身体もほっと一息つく季節ですが、秋は"乾燥"によるトラブルが起こりやすくなるので油断は禁物です。体内の潤いを十分に保つよう心がけ、乾燥のダメージから身体を守りましょう。

概 要

「肺」の潤い不足が乾燥障害の原因
秋は空気の乾燥が気になる季節です。そのため「燥邪」の影響を受けやすく、身体の潤い不足からさまざまな乾燥障害が起こります。
特に気を付けたいのは、燥邪の障害をもっとも受けやすい「肺」です。肺は「潤いを好み、乾燥を嫌う」という性質があるため、燥邪の影響で肺が乾燥した状態になると、まずのどや鼻、気管支などの呼吸器系に不調が起こりやすくなります。
また、肺には「気」を生成したり、水分代謝を調節したりする働きもあり、「衛気(身体の防衛力となる気)」や水分を身体の表面(皮膚や体毛)に送り届けています。この機能によって、身体の防衛力を高めたり、皮膚に潤いを与えたりしているため、燥邪によって肺の機能が低下すると、免疫力が落ちて風邪をひきやすくなったり、皮膚が乾燥した状態になったりするのです。
そのほか、肺と関わりの深い「大腸」も燥邪の影響を受けやすいため、便秘気味になることもあります。呼吸器系の不調や皮膚の乾燥、便秘といった症状を感じたら、肺が潤い不足になっているサインと捉え、早めの養生を心がけましょう。
過ごしやすい今の季節は、身体を休ませて体調を整える大切な時期でもあります。寒い冬を風邪などひかず元気に過ごすためにも、"肺の養生"をポイントに身体をしっかり整えましよう。
夏の疲れが残ると、燥邪の影響を受けやすい
秋は乾燥が気になる季節ですが、健康な人の「肺」は水分や血液で十分に潤っているため、「燥邪」の影響を強く受けることはありません。しかし、夏の疲れを秋まで引きずっていると「肺」は燥邪の影響を受けやすくなり、さまざまな乾燥障害が現れるようになります。
夏の間に次のような障害を受けていた人は要注意。まずは夏の疲れを回復して、冬に向けた潤いある身体づくりを心がけましょう。
大量の発汗や冷房による消耗
大量の発汗、冷房による皮膚への負担、暑さによる睡眠不足といった夏の消耗は、体内の潤い不足を招きます。こうした潤い不足の身体に「燥邪」が入り込むと、乾燥の障害を受けやすくなります。
冷たいものの摂り過ぎなどによる脾胃の疲れ
夏の問、冷たいものの摂り過ぎや暴飲暴食を続けていると、脾胃(消化器系)が弱って栄養がしっかり摂れず、体内の「気・血・水」を生み出す力が低下してしまいます。その結果、身体の潤いが不足して燥邪の影響を受けやすくなってしまいます。

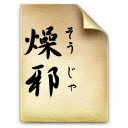
使用漢方薬
次の漢方薬が、乾燥障害・Top・に対してよく効く可能性が高いです。

 をクリック(タップ)→説明表示
をクリック(タップ)→説明表示

処方名:生脈散
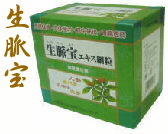
口・鼻の乾燥の方へ
処方名:麦門冬湯
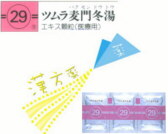
口・鼻の乾燥の方へ
処方名:杞菊地黄丸
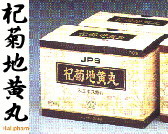
ドライアイの方へ
処方名:当帰養血精

皮膚の乾燥・かゆみの方へ
処方名:麻子仁丸
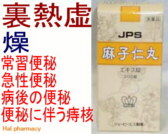
便秘気味(腸の乾燥)の方へ
処方名:潤腸湯
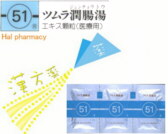
便秘気味(腸の乾燥)の方へ




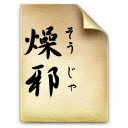
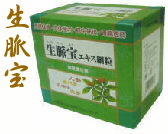 口・鼻の乾燥の方へ
口・鼻の乾燥の方へ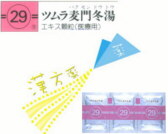 口・鼻の乾燥の方へ
口・鼻の乾燥の方へ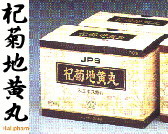 ドライアイの方へ
ドライアイの方へ 皮膚の乾燥・かゆみの方へ
皮膚の乾燥・かゆみの方へ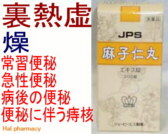 便秘気味(腸の乾燥)の方へ
便秘気味(腸の乾燥)の方へ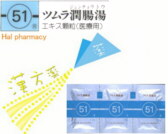 便秘気味(腸の乾燥)の方へ
便秘気味(腸の乾燥)の方へ